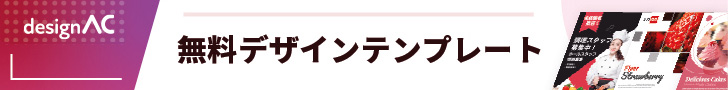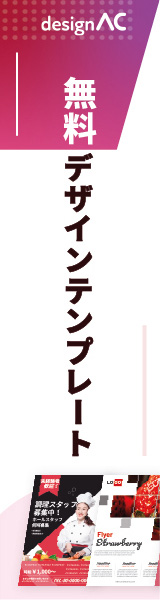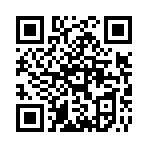2024年11月26日
インド北部・ヒマラヤに棲むヒマラヤタール
山岳地帯に棲むヒマラヤタール 天敵はユキヒョウ

ヒマラヤタールは偶蹄目ウシ科
撮影場所は南紀白浜アドベンチャーワールドです。
このヒマラヤタールはインド北部からヒマラヤで2000~5000メートルという山岳地帯・高地の森林地帯で生活しています。
ということで崖が好きなヤギに近い感じでしょうね。
ここアドベンチャーワールドでも崖を作り群れで生活していました。
天敵もこの付近の山岳地帯で生息している肉食動物のユキヒョウ(どちらも絶滅危惧種)
ウシ科ということで、シカ科のようにツノは生え変わらずメスもツノがあり、ただオスより短いようです。
大きさはヤギよりも大きく比べるとポニーくらいだったように思います。

このヒマラヤタールですが、日本の動物園でも飼育展示している施設は5か所程度と少ないようで、西日本では大分県アフリカンサファリとなっています。
なかなか貴重な動物を見ることが出来ました。

ヒマラヤタールは偶蹄目ウシ科
撮影場所は南紀白浜アドベンチャーワールドです。
このヒマラヤタールはインド北部からヒマラヤで2000~5000メートルという山岳地帯・高地の森林地帯で生活しています。
ということで崖が好きなヤギに近い感じでしょうね。
ここアドベンチャーワールドでも崖を作り群れで生活していました。
天敵もこの付近の山岳地帯で生息している肉食動物のユキヒョウ(どちらも絶滅危惧種)
ウシ科ということで、シカ科のようにツノは生え変わらずメスもツノがあり、ただオスより短いようです。
大きさはヤギよりも大きく比べるとポニーくらいだったように思います。
このヒマラヤタールですが、日本の動物園でも飼育展示している施設は5か所程度と少ないようで、西日本では大分県アフリカンサファリとなっています。
なかなか貴重な動物を見ることが出来ました。
2024年11月23日
世界一美しい容姿のシカ アクシスジカ
背中の斑点が特徴的な美しいアクシスジカ

アクシスジカ:偶蹄目シカ科
この写真は姫路セントラルパークというサファリパークで撮影したものです。
残念ながらツノがあるオスの写真がないのですが、三方向に分岐する立派なツノがとても美しいです。
このアクシスジカはインドでは普通に見られるとのこと。
日本で見られるニホンジカとおおむね大きさは同じです(ちなみに北海道にいるエゾシカはかなり大きい)
背中の白い斑点はオス・メスともにあり、この模様によりアクシスジカは世界一美しいといわれるそう。


アクシスジカは性格は大人しいらしく、オス同士のケンカでもツノを突き合わせることはほとんどないそうです。
写真のように群れで暮らし、その群れはときには数百頭にもなるときがあるというから爽快でしょうね!!
生息地は見晴らしの良い平原で草や木の実などがあるところです。
草が少なくなる季節はハヌマンラングールと行動を共に

写真のお猿さんがハヌマンラングール
こちらは山口県宇部市のときわ動物園で撮影したものです。
食料の乏しい季節は、樹上生活者のハヌマンラングールが落とす木の実を食べるために共同生活をしている。
たぶん天敵が現れたときなど、お猿さんの警戒する声で逃げたりするんでしょうか??
アクシスジカ:偶蹄目シカ科
この写真は姫路セントラルパークというサファリパークで撮影したものです。
残念ながらツノがあるオスの写真がないのですが、三方向に分岐する立派なツノがとても美しいです。
このアクシスジカはインドでは普通に見られるとのこと。
日本で見られるニホンジカとおおむね大きさは同じです(ちなみに北海道にいるエゾシカはかなり大きい)
背中の白い斑点はオス・メスともにあり、この模様によりアクシスジカは世界一美しいといわれるそう。
アクシスジカは性格は大人しいらしく、オス同士のケンカでもツノを突き合わせることはほとんどないそうです。
写真のように群れで暮らし、その群れはときには数百頭にもなるときがあるというから爽快でしょうね!!
生息地は見晴らしの良い平原で草や木の実などがあるところです。
草が少なくなる季節はハヌマンラングールと行動を共に
写真のお猿さんがハヌマンラングール
こちらは山口県宇部市のときわ動物園で撮影したものです。
食料の乏しい季節は、樹上生活者のハヌマンラングールが落とす木の実を食べるために共同生活をしている。
たぶん天敵が現れたときなど、お猿さんの警戒する声で逃げたりするんでしょうか??
2024年11月22日
日本に2か所だけ 世界最小の鹿 プーズー
南米のチリにしか生息しない 世界最小の鹿 プーズー

神戸どうぶつ王国で撮影
偶蹄目シカ科で、同じシカの仲間で日本にも生息している「キョン」よりも小さい!!
南米のチリに生息しているプーズーです。
(説明には生息地アルゼンチンと書いてありますが、どうやら絶滅したらしい)
オスには10センチ程度のツノがありますが、メスにはありません。
シカ科なのでツノは生え変わります。(このあたりが容姿がシカに似ていてもツノが生え変わらないウシ科と違うところ)
神戸どうぶつ王国では「プーズー」の説明が書いてあります

プーズーの飼育展示施設は西日本では神戸どうぶつ王国だけ

このプーズーですが、西日本ではここ神戸どうぶつ王国だけで、あとは埼玉県こども動物自然公園で見られるそうです。
赤ちゃんはほかのシカと同じように白い斑点があり、とてもキュートです。
ちなみに神戸どうぶつ王国 入場料はほかの動物園より高めですが、ドッグショーがあったり鳥の
パフォーマンスもあり、それなりの施設でとても楽しめました。
神戸どうぶつ王国で撮影
偶蹄目シカ科で、同じシカの仲間で日本にも生息している「キョン」よりも小さい!!
南米のチリに生息しているプーズーです。
(説明には生息地アルゼンチンと書いてありますが、どうやら絶滅したらしい)
オスには10センチ程度のツノがありますが、メスにはありません。
シカ科なのでツノは生え変わります。(このあたりが容姿がシカに似ていてもツノが生え変わらないウシ科と違うところ)
神戸どうぶつ王国では「プーズー」の説明が書いてあります
プーズーの飼育展示施設は西日本では神戸どうぶつ王国だけ
このプーズーですが、西日本ではここ神戸どうぶつ王国だけで、あとは埼玉県こども動物自然公園で見られるそうです。
赤ちゃんはほかのシカと同じように白い斑点があり、とてもキュートです。
ちなみに神戸どうぶつ王国 入場料はほかの動物園より高めですが、ドッグショーがあったり鳥の
パフォーマンスもあり、それなりの施設でとても楽しめました。
2024年11月19日
キュートなナマケモノの赤ちゃん
フタユビナマケモノの赤ちゃん 人工保育中

和歌山県にあるアドベンチャーワールドから人工保育中の「フタユビナマケモノ」の赤ちゃん
8月に誕生したそうなので、この写真は生後2か月というところです。
どういう理由で人工保育になったのかは書かれていなかったように記憶しています。
フタユビナマケモノの説明が書いてありました

ナマケモノは南アメリカから中央アメリカの密林地帯に生息し、ミユビナマケモノ科とフタユビナマケモノ科がいます。
この子はフタユビナマケモノですが、ツメ(ゆび)が見えなかったので子どものうちは親に抱かれているので必要ないのかな??
幸せそうな顔で眠るフタユビナマケモノの赤ちゃん

大人はかぎ爪で木の枝に、おなかを上にしてぶら下がっていますが、子ども・赤ちゃんはおなかの上に乗るような態勢なのでしょうか?
ナマケモノはほとんど地上に降りることなく排泄のときのみ地上に降りるそうです。
名前の通りで怠けてはいないのですが、ほぼ動かないのは最低限の食事でエネルギーを使わないようにしているから
少し目が離れていて、潰れた顔がなんともキュートです。
和歌山県にあるアドベンチャーワールドから人工保育中の「フタユビナマケモノ」の赤ちゃん
8月に誕生したそうなので、この写真は生後2か月というところです。
どういう理由で人工保育になったのかは書かれていなかったように記憶しています。
フタユビナマケモノの説明が書いてありました
ナマケモノは南アメリカから中央アメリカの密林地帯に生息し、ミユビナマケモノ科とフタユビナマケモノ科がいます。
この子はフタユビナマケモノですが、ツメ(ゆび)が見えなかったので子どものうちは親に抱かれているので必要ないのかな??
幸せそうな顔で眠るフタユビナマケモノの赤ちゃん
大人はかぎ爪で木の枝に、おなかを上にしてぶら下がっていますが、子ども・赤ちゃんはおなかの上に乗るような態勢なのでしょうか?
ナマケモノはほとんど地上に降りることなく排泄のときのみ地上に降りるそうです。
名前の通りで怠けてはいないのですが、ほぼ動かないのは最低限の食事でエネルギーを使わないようにしているから
少し目が離れていて、潰れた顔がなんともキュートです。
2024年11月18日
仔シマウマの足の長さの秘密とは
捕食される側の装飾動物は敵から逃げることが一番大切なこと

とくにシマウマだけというわけではありませんが、トラやライオンの肉食動物から逃げるには、とにかく早く走ることが必要です。
ですので、シマウマも子どもは足のほうが早期に完成したものとなります。
こちらが子どものシマウマ(グラントシマウマ)

どうでしょうか?
上の写真が大人のシマウマですが、ほぼ足の長さが同じに見えるでしょうか?
同じ草食動物でも、大きなお母さんキリンから後ろ足でキックされたらライオンでも死んでしまいますしね。
ですから赤ちゃんキリンが対象でも、そうそう近づくことは危険です。
微笑ましい シマウマの親子

こ
の写真を撮影した「広島市安佐動物公園」では、たくさんのグラントシマウマを飼育展示しています。
同じ敷地内で多頭数で展示する動物園は珍しいそう
けどシマウマはけっこう気が荒いので、蹴ったり噛みついたりするようで、首にひづめの跡などがあります。
シマウマたちの生活しているアフリカのサバンナでは、群れで行動しているのでケンカも必然なのかもしれませんね。
とくにシマウマだけというわけではありませんが、トラやライオンの肉食動物から逃げるには、とにかく早く走ることが必要です。
ですので、シマウマも子どもは足のほうが早期に完成したものとなります。
こちらが子どものシマウマ(グラントシマウマ)
どうでしょうか?
上の写真が大人のシマウマですが、ほぼ足の長さが同じに見えるでしょうか?
同じ草食動物でも、大きなお母さんキリンから後ろ足でキックされたらライオンでも死んでしまいますしね。
ですから赤ちゃんキリンが対象でも、そうそう近づくことは危険です。
微笑ましい シマウマの親子
こ
の写真を撮影した「広島市安佐動物公園」では、たくさんのグラントシマウマを飼育展示しています。
同じ敷地内で多頭数で展示する動物園は珍しいそう
けどシマウマはけっこう気が荒いので、蹴ったり噛みついたりするようで、首にひづめの跡などがあります。
シマウマたちの生活しているアフリカのサバンナでは、群れで行動しているのでケンカも必然なのかもしれませんね。
2024年11月16日
シマウマのひとりごと
シマウマは同じように見えて縞模様によって種類が違う
サバンナシマウマのうちのグラントシマウマ

シマウマは奇蹄目ウマ科(奇数のひづめ)
ひづめが1本ですので奇数の蹄のウマの仲間という意味です。
この写真の子はサバンナシマウマの グラントシマウマという種類になります。
サバンナシマウマの仲間はチャップマンシマウマがいます。
日本の動物園等で見られる種類は、グラントシマウマ・チャップマンシマウマ・グレビーシマウマ・ハートマンヤマシマウマの4種類です。
説明が難しいのですが、写真を見比べると、なんとなく区別ができるようになるかと・・・

こちらがグラントシマウマの幼獣です。
自然に近い集団で飼育展示している動物園が「広島市安佐動物公園」で、このグラントシマウマが複数で走り回っています。
ただシマウマは気が荒いので、ひづめで蹴られた足あとが首に付いていたり、けっこう痛々しいのですが、それも自然なことかと思います。
サバンナシマウマのうちのチャップマンシマウマ


写真で見るとグラントシマウマに似ていますが、お尻のほう 黒い模様のあいだに茶色い線が入っています。
どこの動物園でも動物たちの種類は出ていると思うのですが、細かい見分け方まで書いていないので、ご参考になれば幸いです。
大型になるハートマンヤマシマウマ

ヤマシマウマの生息地はアフリカの南部
この写真では見えにくいのですが、のどに肉だれがあります。
にわとりのトサカの逆バージョンと思っていただければ・・・
ちなみにハートマンというのは発見者の名前で深い意味はありません!!
サバンナシマウマのうちのグラントシマウマ
シマウマは奇蹄目ウマ科(奇数のひづめ)
ひづめが1本ですので奇数の蹄のウマの仲間という意味です。
この写真の子はサバンナシマウマの グラントシマウマという種類になります。
サバンナシマウマの仲間はチャップマンシマウマがいます。
日本の動物園等で見られる種類は、グラントシマウマ・チャップマンシマウマ・グレビーシマウマ・ハートマンヤマシマウマの4種類です。
説明が難しいのですが、写真を見比べると、なんとなく区別ができるようになるかと・・・
こちらがグラントシマウマの幼獣です。
自然に近い集団で飼育展示している動物園が「広島市安佐動物公園」で、このグラントシマウマが複数で走り回っています。
ただシマウマは気が荒いので、ひづめで蹴られた足あとが首に付いていたり、けっこう痛々しいのですが、それも自然なことかと思います。
サバンナシマウマのうちのチャップマンシマウマ
写真で見るとグラントシマウマに似ていますが、お尻のほう 黒い模様のあいだに茶色い線が入っています。
どこの動物園でも動物たちの種類は出ていると思うのですが、細かい見分け方まで書いていないので、ご参考になれば幸いです。
大型になるハートマンヤマシマウマ

ヤマシマウマの生息地はアフリカの南部
この写真では見えにくいのですが、のどに肉だれがあります。
にわとりのトサカの逆バージョンと思っていただければ・・・
ちなみにハートマンというのは発見者の名前で深い意味はありません!!
2024年11月15日
ブラックバックなブラックバック
背中が黒いからブラックバックなのだが・・・

偶蹄目ウシ科(ひづめが偶数でツノが生え変わらないウシの仲間)
生息地はインド・ネパールあたり
ブラックバックはオスのリーダーにメスが複数と幼獣や群れを追われたオスでハーレムを形成します。
背中が黒いのでブラックバックですが、メスは普通にベージュというか黄色というか・・・
特にオスにはねじれたツノがあり、ワインのコルク抜きのようです。

こちらがメスのブラックバック
このブラックバックたちは警戒心が強く、飼育員さんたちでも近づくと逃げていくんだそうです。
目が離れているのはそのためで、かなり視界は広いんでしょうねぇ~
で、足も速くて時速70㎞ほどで走る(逃げる?)そうです。

こちらはブラックバックの幼獣ですが、なんとも可愛らしい♪
このくらいから人間が近くにいると慣れるのかもしれませんね。
上の2枚の写真は広島市安佐動物
下の幼獣は香川県にある白鳥動物園で撮影しました。
偶蹄目ウシ科(ひづめが偶数でツノが生え変わらないウシの仲間)
生息地はインド・ネパールあたり
ブラックバックはオスのリーダーにメスが複数と幼獣や群れを追われたオスでハーレムを形成します。
背中が黒いのでブラックバックですが、メスは普通にベージュというか黄色というか・・・
特にオスにはねじれたツノがあり、ワインのコルク抜きのようです。
こちらがメスのブラックバック
このブラックバックたちは警戒心が強く、飼育員さんたちでも近づくと逃げていくんだそうです。
目が離れているのはそのためで、かなり視界は広いんでしょうねぇ~
で、足も速くて時速70㎞ほどで走る(逃げる?)そうです。
こちらはブラックバックの幼獣ですが、なんとも可愛らしい♪
このくらいから人間が近くにいると慣れるのかもしれませんね。
上の2枚の写真は広島市安佐動物
下の幼獣は香川県にある白鳥動物園で撮影しました。
2021年07月16日
ヒグマが旭川の市内の川に?
ヒグマの生息域が拡大されている危機的状況

Yahooニュースで旭川のほぼ中心地である、花咲橋あたりで川にクマがいたという記事がありました。
1960年に旭川で生まれて、ヒグマが旭川に出たなんて話は60年生きてきて初めて聞きますすが・・・・ ホントかなぁ・・・
たぶん大雪山から降りてきたとしても、一番近いと思われる距離でも川沿いに歩いてきて30km以上はあるはずです。

ヒグマがなぜ増えたのか?ということは、エサがないということは言われてきています。
エゾシカも非常に増えているのは、紛れもなく天敵がいなくなったから。
エゾシカの天敵であったエゾオオカミですが、1896年に駆除により、北海道からエゾオオカミが絶滅したと伝えられています。
中国で、少し前(1960年ころ)ですがスズメ打倒運動というのが行われました。
市民は鍋・フライパン・バケツ・洗面器といった音の鳴る物を叩いて、スズメが木の枝で休む隙を与えず、空から死んで落ちるようにした・・・
スズメを駆除することで生態バランスが崩れ、天敵のいなくなった虫が農作物を荒らすことに気づいた毛は、スズメ撲滅運動の停止を命じて今度は「益鳥」として"名誉回復"したが、そんなことで減ったスズメは急には増えることがなく、虫がどんどん増えて中国では大飢饉がはっせいしたわけです。
なまじ人間が野生動物を管理することを、日本人も忘れてはいけない!!
ちなみにオオカミは人間を恐れるために、人間の生息域に出てくることはないといいます。
Yahooニュースで旭川のほぼ中心地である、花咲橋あたりで川にクマがいたという記事がありました。
1960年に旭川で生まれて、ヒグマが旭川に出たなんて話は60年生きてきて初めて聞きますすが・・・・ ホントかなぁ・・・
たぶん大雪山から降りてきたとしても、一番近いと思われる距離でも川沿いに歩いてきて30km以上はあるはずです。
ヒグマがなぜ増えたのか?ということは、エサがないということは言われてきています。
エゾシカも非常に増えているのは、紛れもなく天敵がいなくなったから。
エゾシカの天敵であったエゾオオカミですが、1896年に駆除により、北海道からエゾオオカミが絶滅したと伝えられています。
中国で、少し前(1960年ころ)ですがスズメ打倒運動というのが行われました。
市民は鍋・フライパン・バケツ・洗面器といった音の鳴る物を叩いて、スズメが木の枝で休む隙を与えず、空から死んで落ちるようにした・・・
スズメを駆除することで生態バランスが崩れ、天敵のいなくなった虫が農作物を荒らすことに気づいた毛は、スズメ撲滅運動の停止を命じて今度は「益鳥」として"名誉回復"したが、そんなことで減ったスズメは急には増えることがなく、虫がどんどん増えて中国では大飢饉がはっせいしたわけです。
なまじ人間が野生動物を管理することを、日本人も忘れてはいけない!!
ちなみにオオカミは人間を恐れるために、人間の生息域に出てくることはないといいます。
2020年12月13日
長崎バイオパーク行ってきまして②
アカナハナグマというのですが、アライグマの仲間らしい

アカナハナグマの生息地は南アメリカの中央部で、かなり広範囲に生息しているようです。
クマと言えば、ヒグマとかツキノワグマなんかを想像しますが、専門的にはこのアカハナグマは食肉目アライグマ科となります。
アライグマなんかの仲間ということですね~
ちなみに熊は食肉目のクマ科ということで同じ肉食動物ではありが、まったく別ものの動物です・・・
シッポのシマシマやら木に登るのを見ると、ほかのサイトでは書いていませんがレッサーパンダの仲間かな?というところで違和感がない気がします。

「あ 電線に スズメが三羽止まってた」
すいません 小松政夫さんが先日亡くなったので、フレーズを使わせてもらいました (;^_^A
やっぱりシッポが長い動物ですから、バランスとるのが上手ですよね!!
この長崎バイオパークでは、動物ごとにエサの自動販売機があるのが特徴的です。
もちろんこのアカナハナグマのコーナーにもあるのですが、人間が歩く通路に渡り廊下のように樹木を渡してあるところがあり、そこで火ばさみでエサを与えることができます。
もう子供たちに大人気でしたねぇ~
アカハナグマを見れる動物園は、広島県(福山市動物園)から西では唯一、長崎バイオパークだけです!!
もちろん九州ではここだけで飼育展示されています。
なんせカワイイので、ぜひアカナハナグマのファンになって欲しいですねぇ


くろすけのブログで使っている画像などは 「写真AC」 にて(一部無料)で販売していますので、検索してみてください。
アカナハナグマの生息地は南アメリカの中央部で、かなり広範囲に生息しているようです。
クマと言えば、ヒグマとかツキノワグマなんかを想像しますが、専門的にはこのアカハナグマは食肉目アライグマ科となります。
アライグマなんかの仲間ということですね~
ちなみに熊は食肉目のクマ科ということで同じ肉食動物ではありが、まったく別ものの動物です・・・
シッポのシマシマやら木に登るのを見ると、ほかのサイトでは書いていませんがレッサーパンダの仲間かな?というところで違和感がない気がします。
「あ 電線に スズメが三羽止まってた」
すいません 小松政夫さんが先日亡くなったので、フレーズを使わせてもらいました (;^_^A
やっぱりシッポが長い動物ですから、バランスとるのが上手ですよね!!
この長崎バイオパークでは、動物ごとにエサの自動販売機があるのが特徴的です。
もちろんこのアカナハナグマのコーナーにもあるのですが、人間が歩く通路に渡り廊下のように樹木を渡してあるところがあり、そこで火ばさみでエサを与えることができます。
もう子供たちに大人気でしたねぇ~
アカハナグマを見れる動物園は、広島県(福山市動物園)から西では唯一、長崎バイオパークだけです!!
もちろん九州ではここだけで飼育展示されています。
なんせカワイイので、ぜひアカナハナグマのファンになって欲しいですねぇ
くろすけのブログで使っている画像などは 「写真AC」 にて(一部無料)で販売していますので、検索してみてください。
2020年12月10日
知られざるカワイイ動物10選⑩
福山市動物園のパルマヤブワラビーのかわいい画像

「いらっしゃいませ」とあいさつしてくれているパルマヤブワラビーのお母さんです。
下の写真は食事のために袋から出てきたところを撮影した赤ちゃんワラビー (=^・^=)

ワラビーは小型のカンガルーで、生息地は同じくオーストラリアです。
有袋類というのも同じで、未熟児で出産して袋のなかで育てます。
カンガルーって、ちょっと大柄であまり可愛くない・・・
なんとなく態度も横暴な気がするのは人間だからか?(笑)

ワラビーはペットショップで販売されていたことから、以前のブログで飼育方法を書いたことがありました。
まぁ~一般家庭では、なかなか飼育スペースを作れなかったりするので飼養するのは並大抵ではありませんが、不可能ではありません。
おススメすることはありませんが、興味のある方は飼育方法を調べてみてはいかがでしょうか?
「くろすけ ワラビー 飼育」 で検索してみてください。
ただ、決して簡単ではないですが・・・ (;^_^A
「いらっしゃいませ」とあいさつしてくれているパルマヤブワラビーのお母さんです。
下の写真は食事のために袋から出てきたところを撮影した赤ちゃんワラビー (=^・^=)
ワラビーは小型のカンガルーで、生息地は同じくオーストラリアです。
有袋類というのも同じで、未熟児で出産して袋のなかで育てます。
カンガルーって、ちょっと大柄であまり可愛くない・・・
なんとなく態度も横暴な気がするのは人間だからか?(笑)
ワラビーはペットショップで販売されていたことから、以前のブログで飼育方法を書いたことがありました。
まぁ~一般家庭では、なかなか飼育スペースを作れなかったりするので飼養するのは並大抵ではありませんが、不可能ではありません。
おススメすることはありませんが、興味のある方は飼育方法を調べてみてはいかがでしょうか?
「くろすけ ワラビー 飼育」 で検索してみてください。
ただ、決して簡単ではないですが・・・ (;^_^A